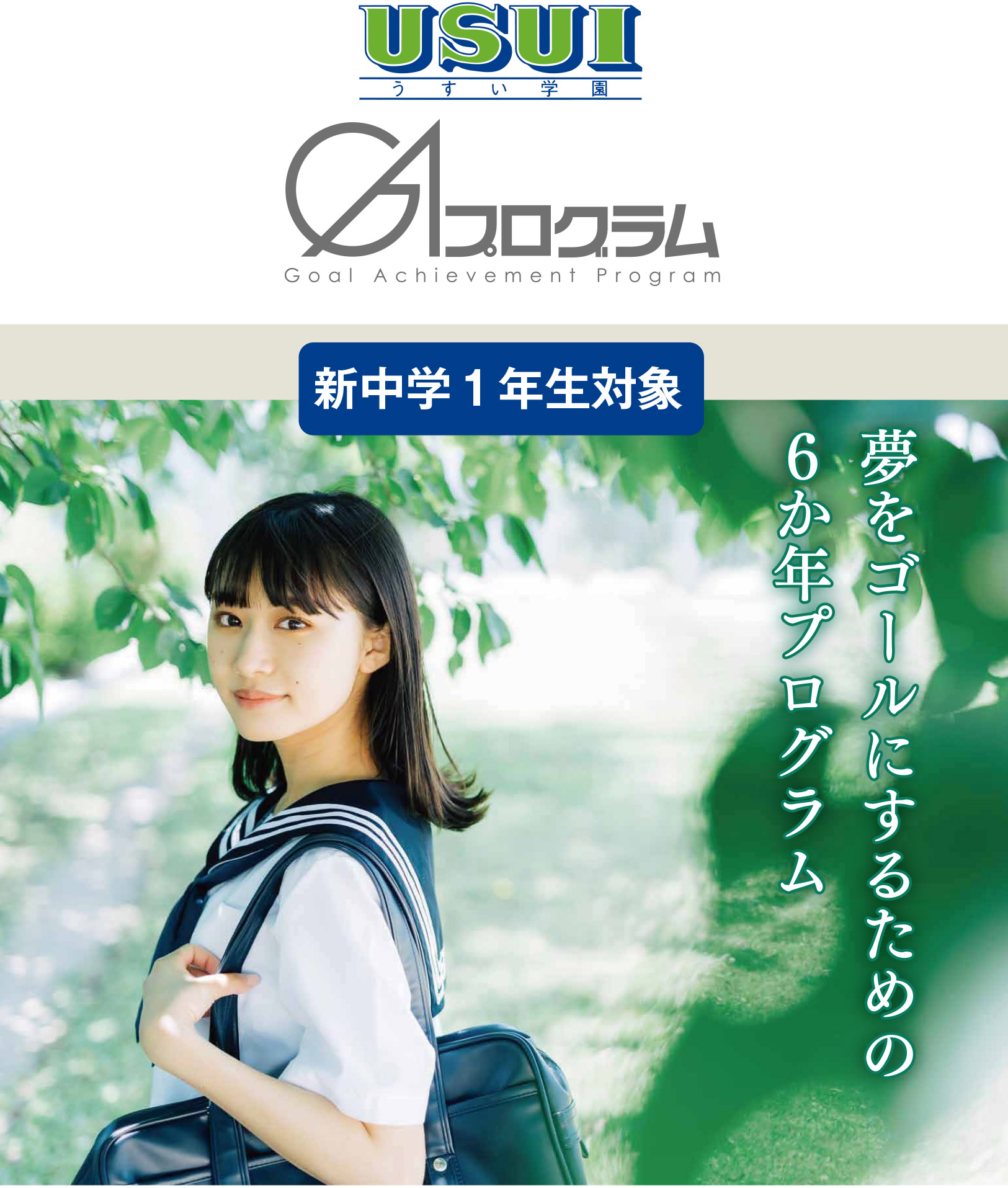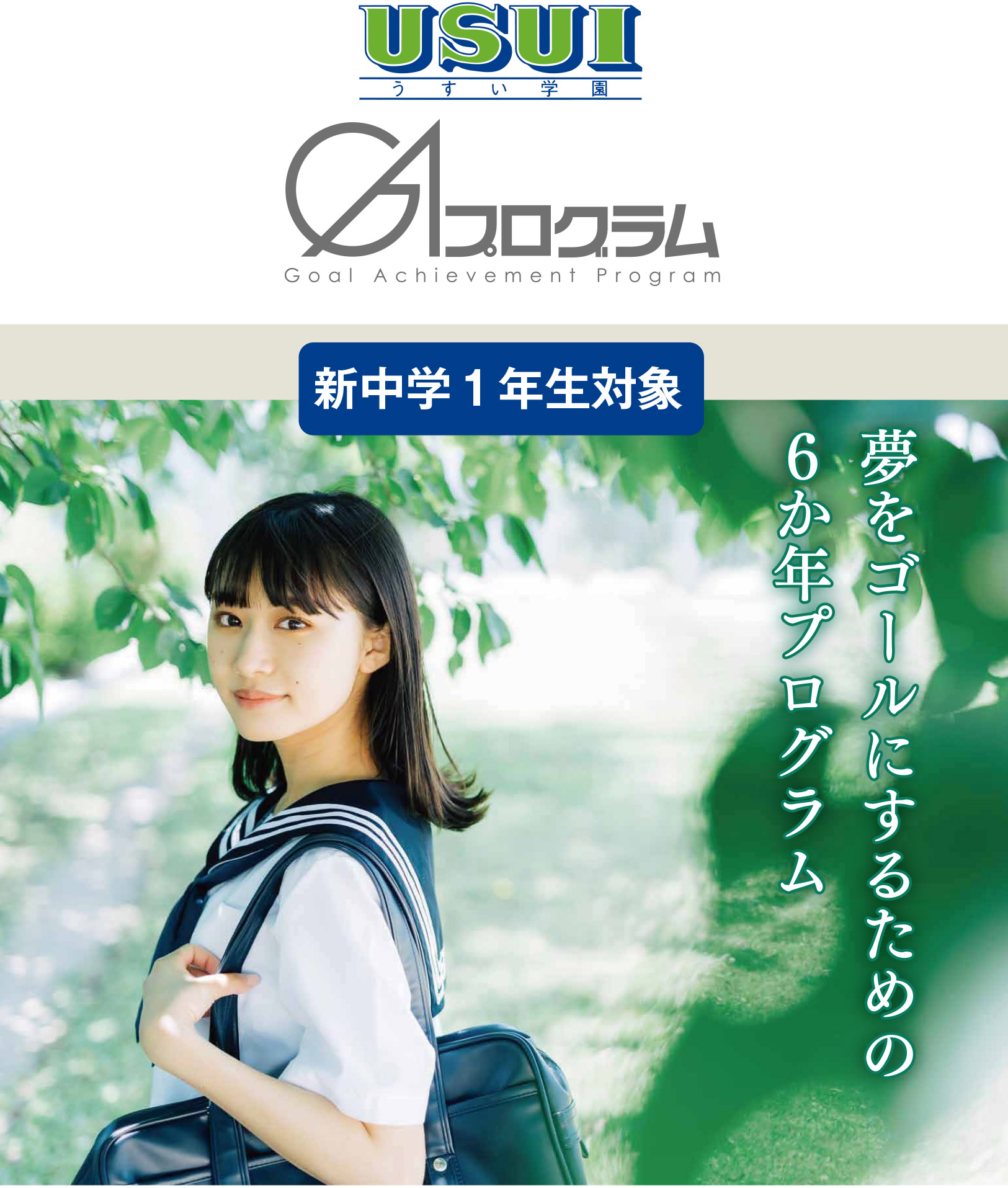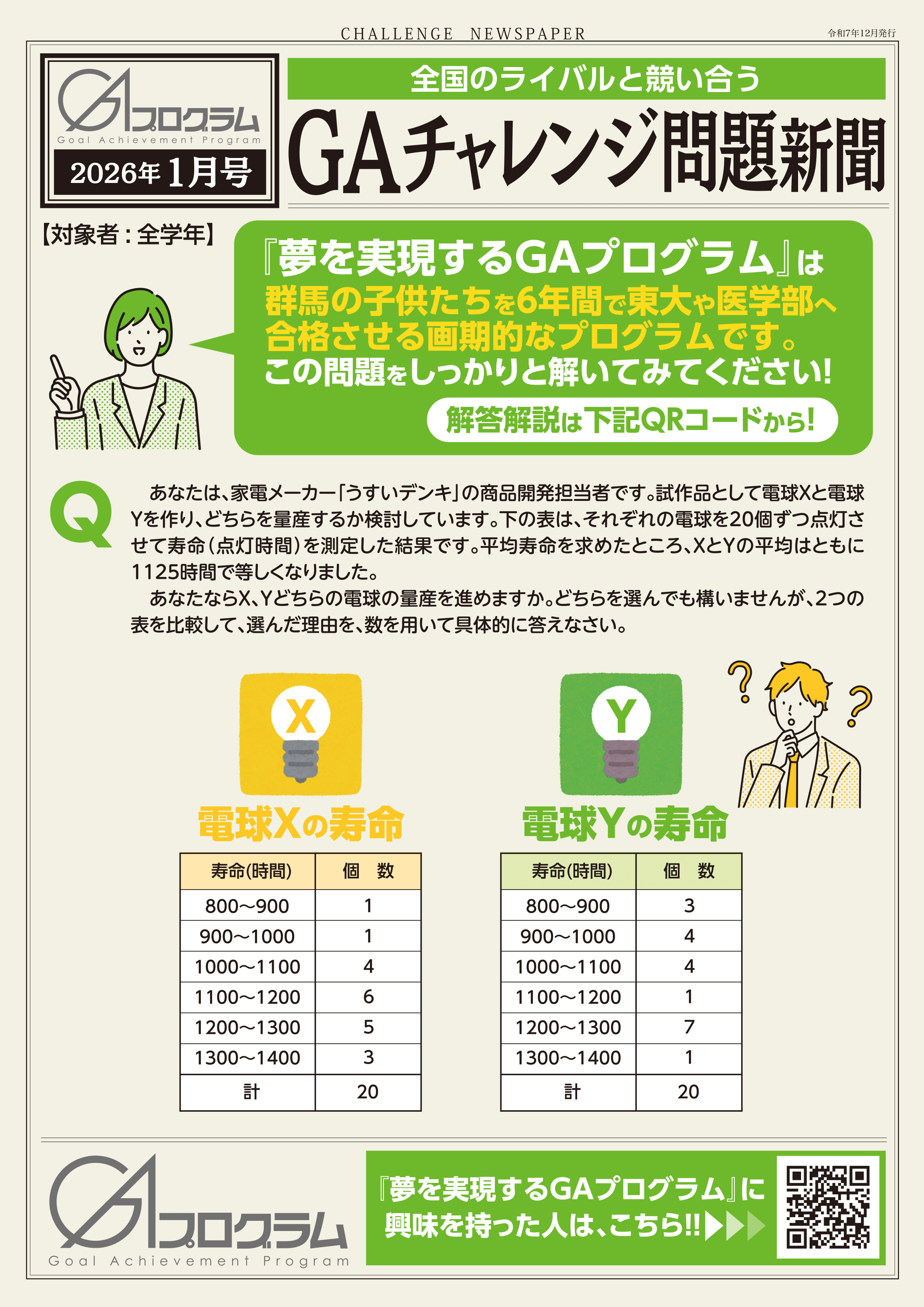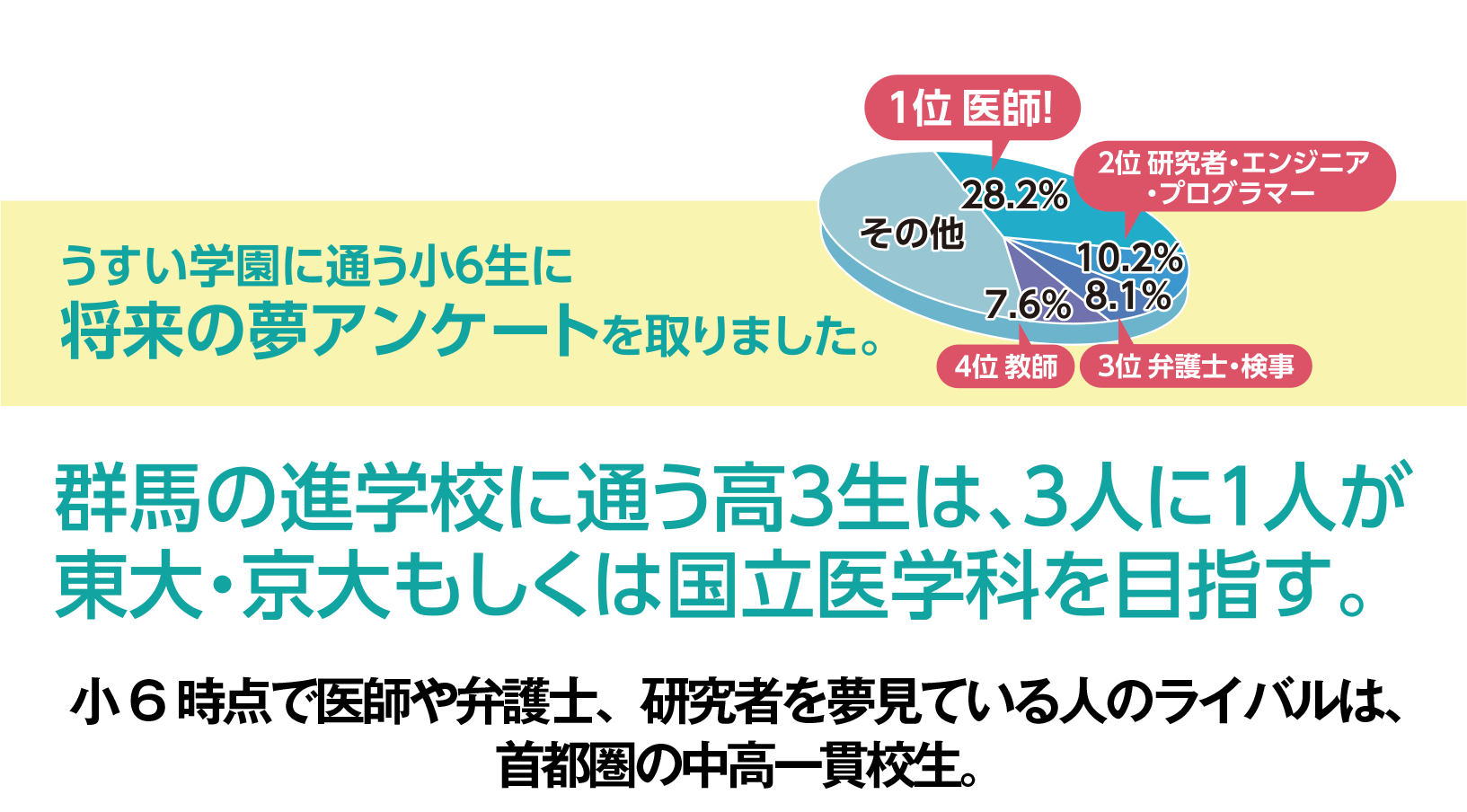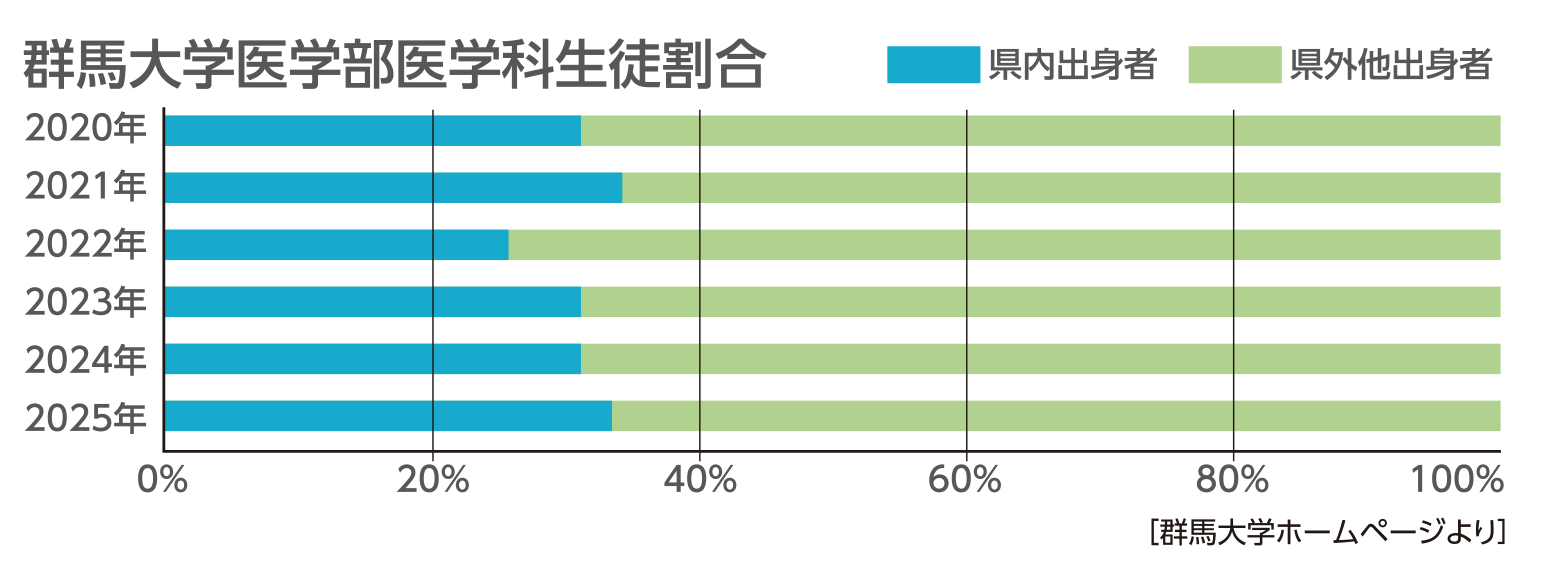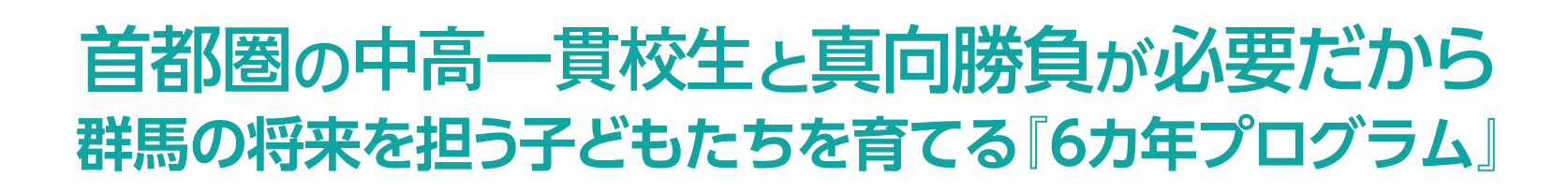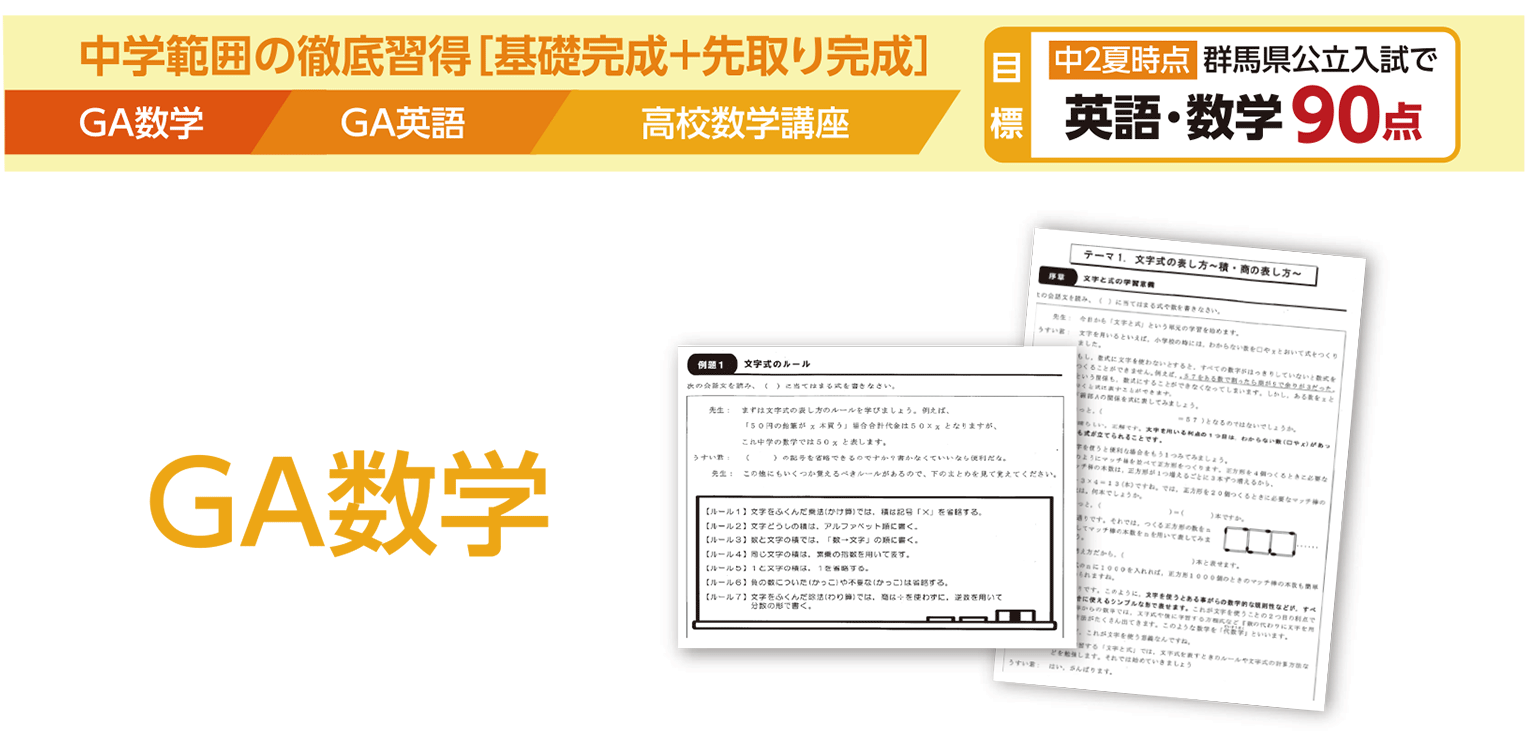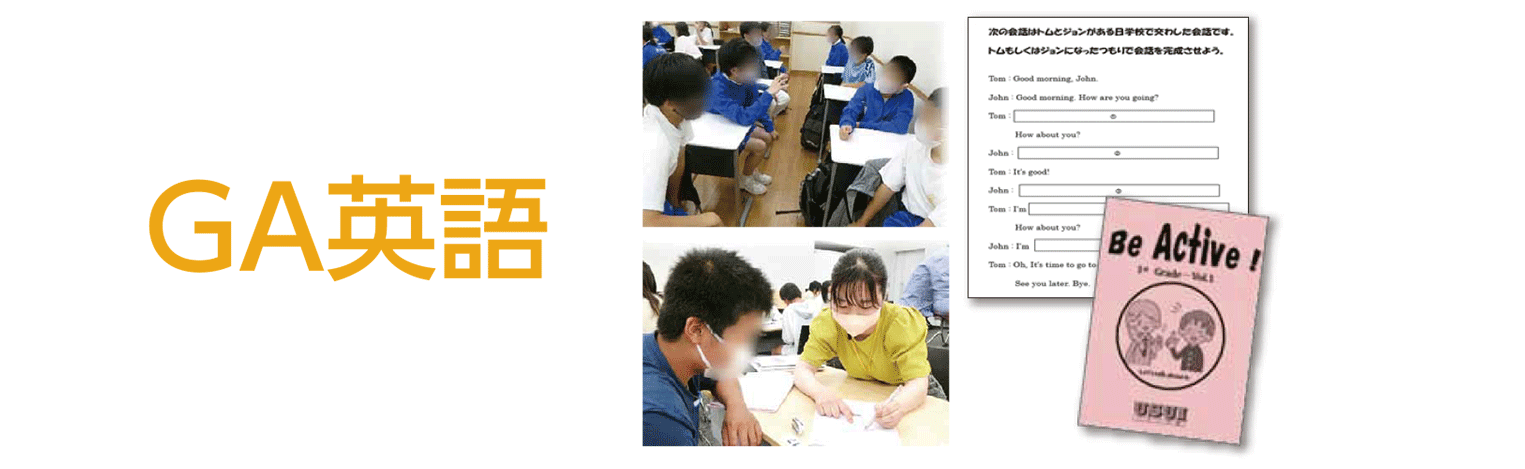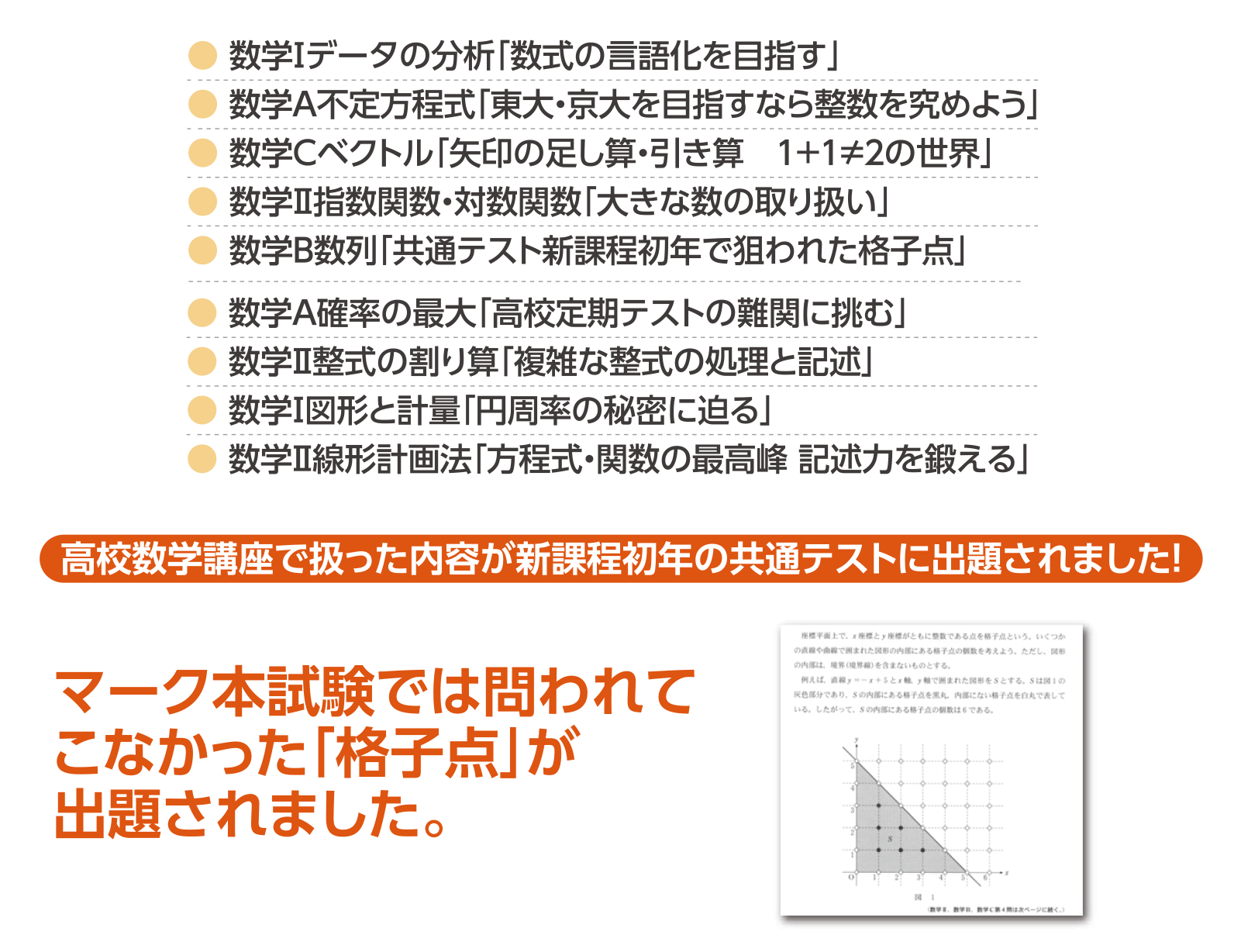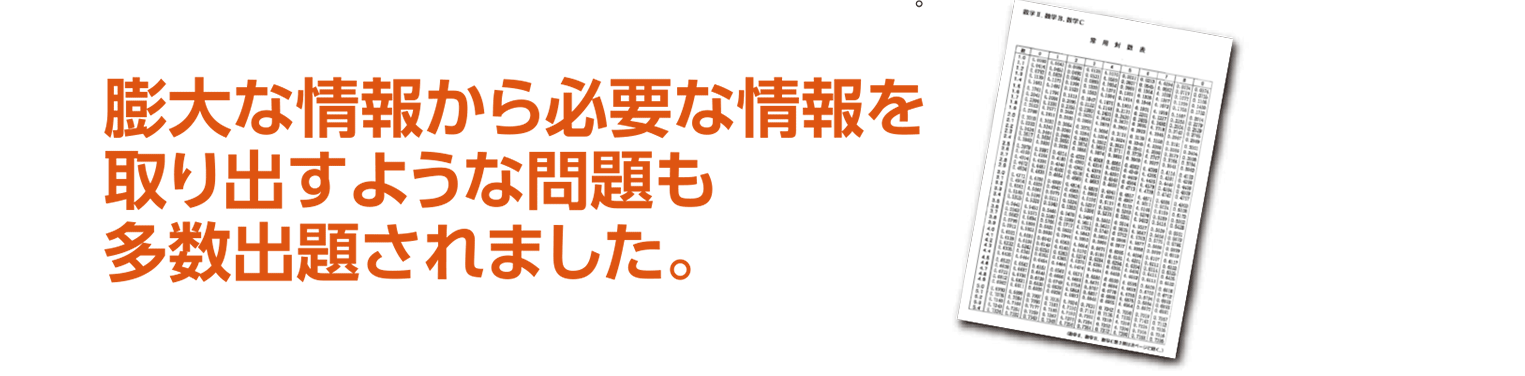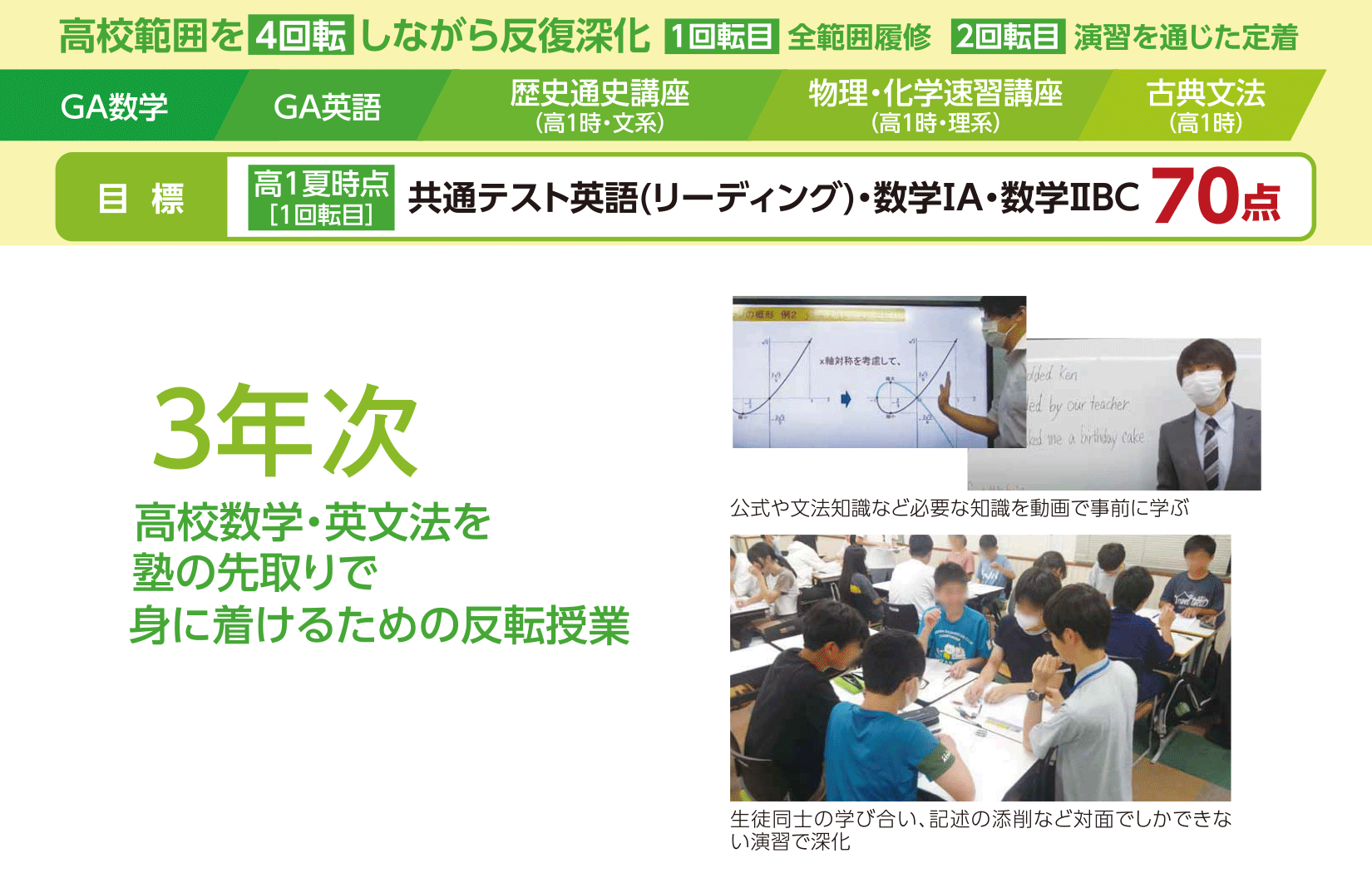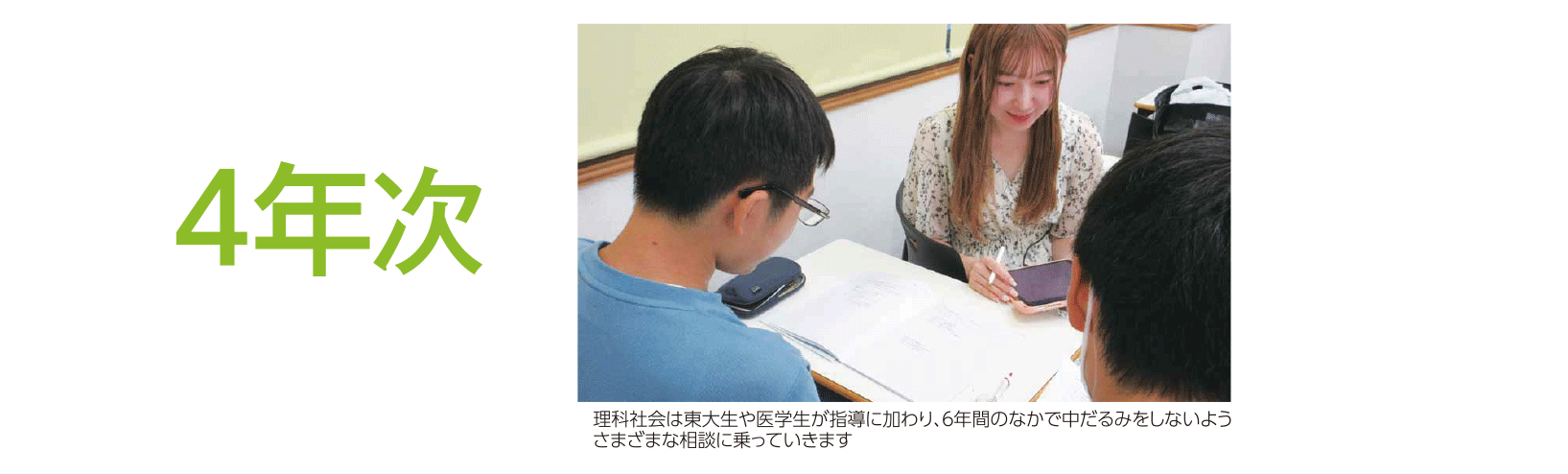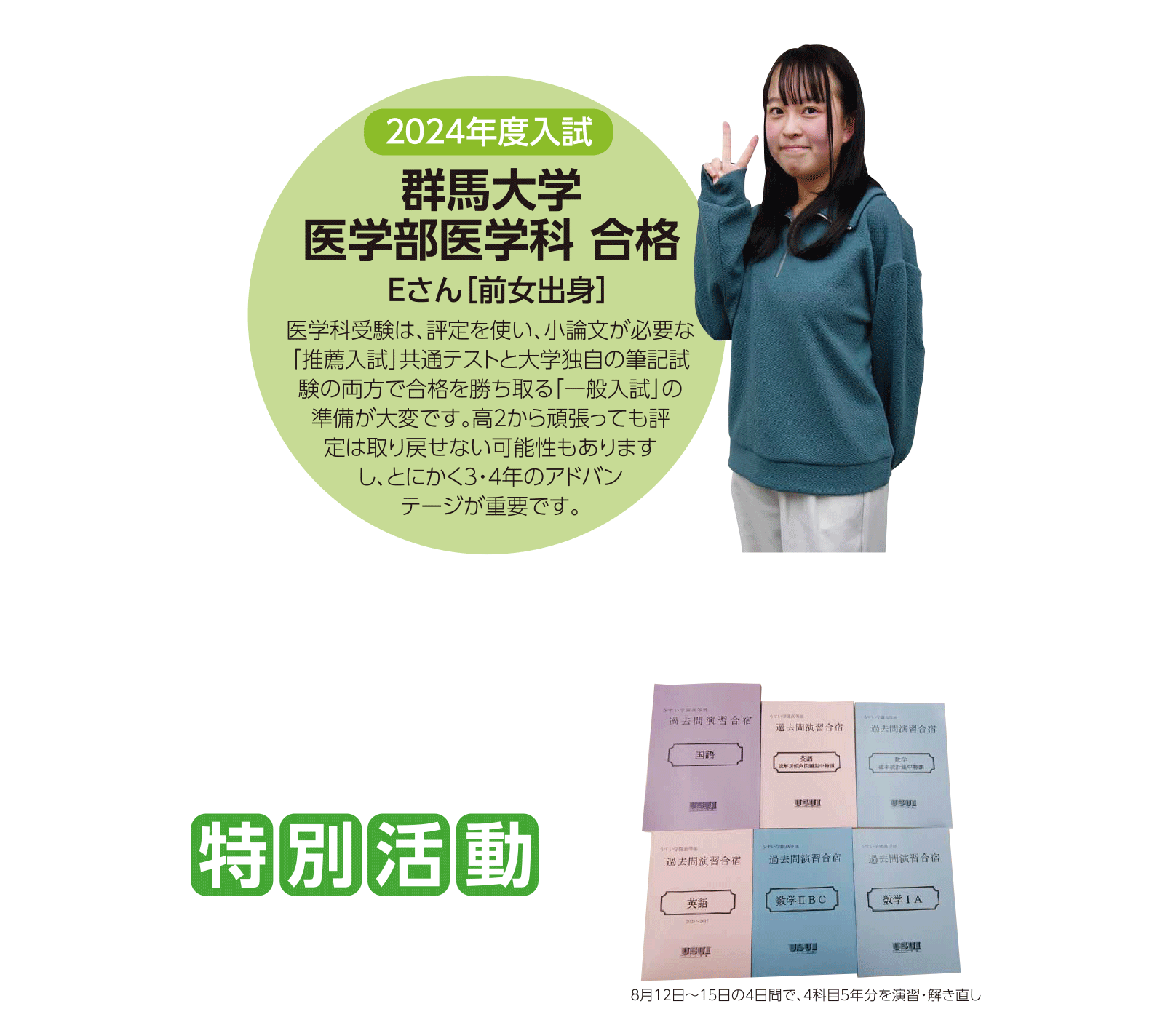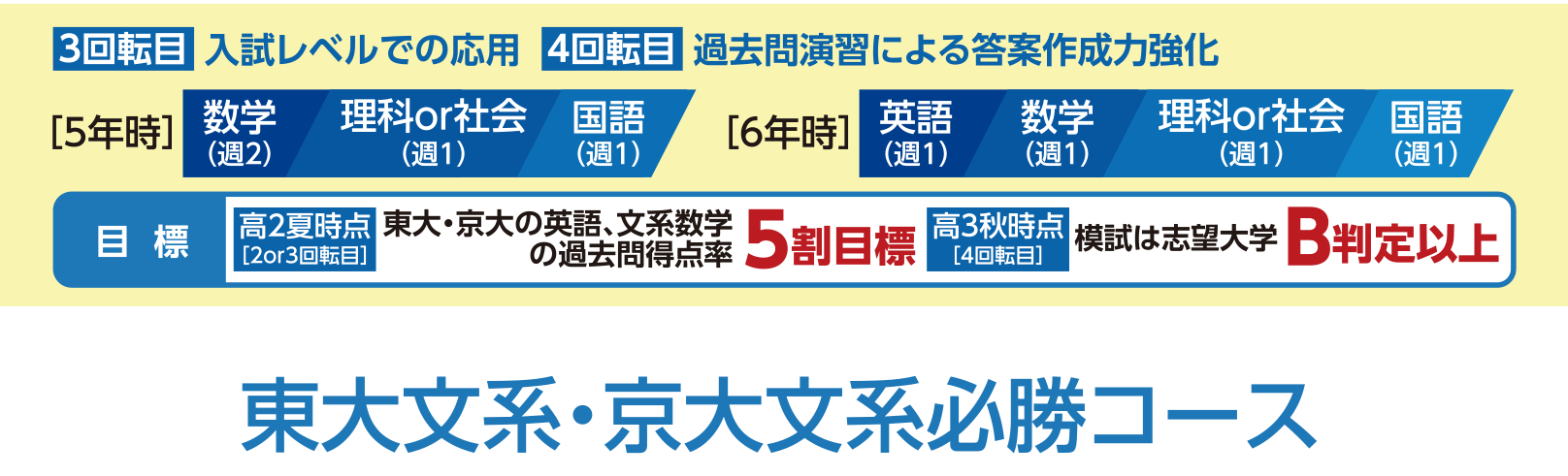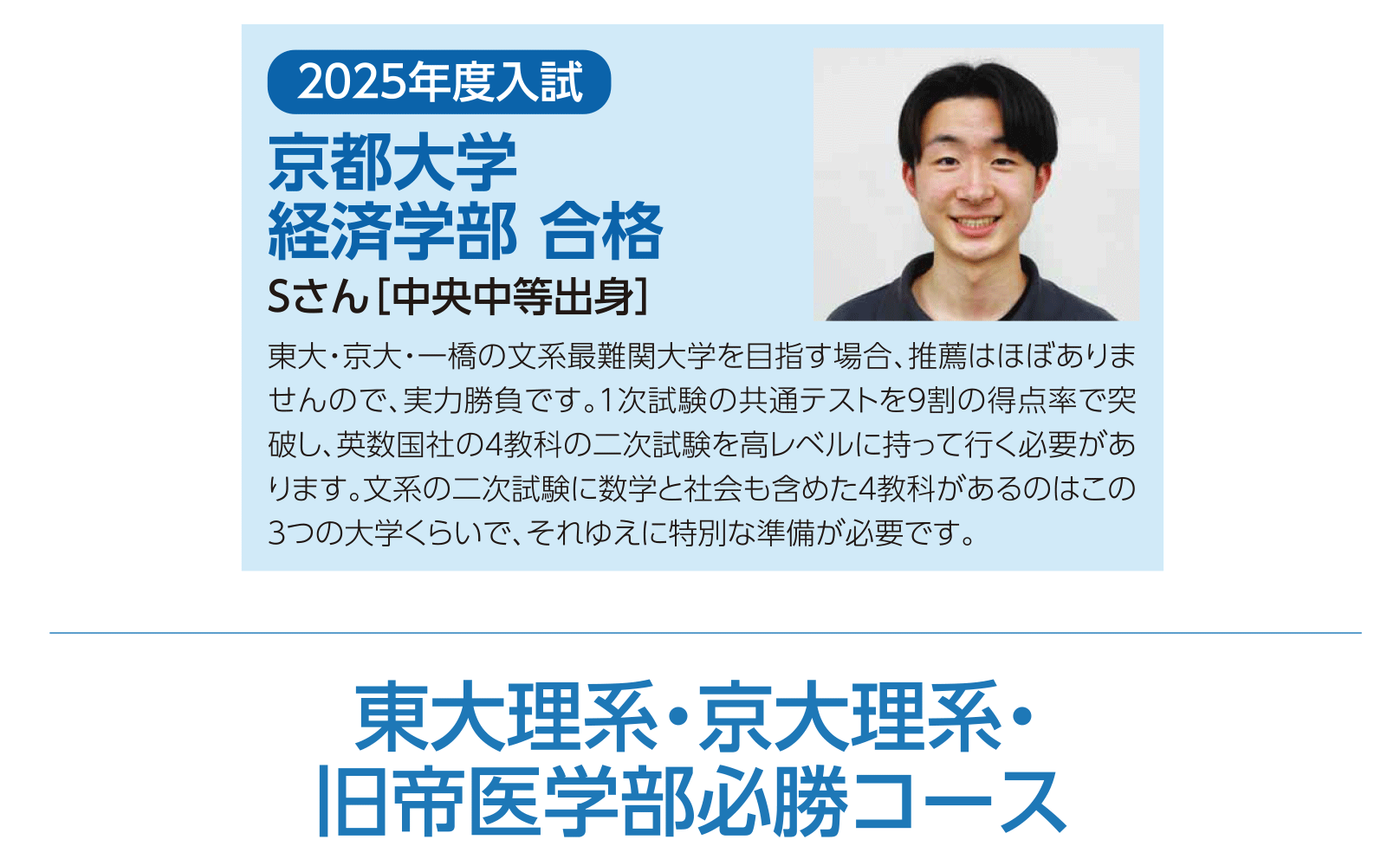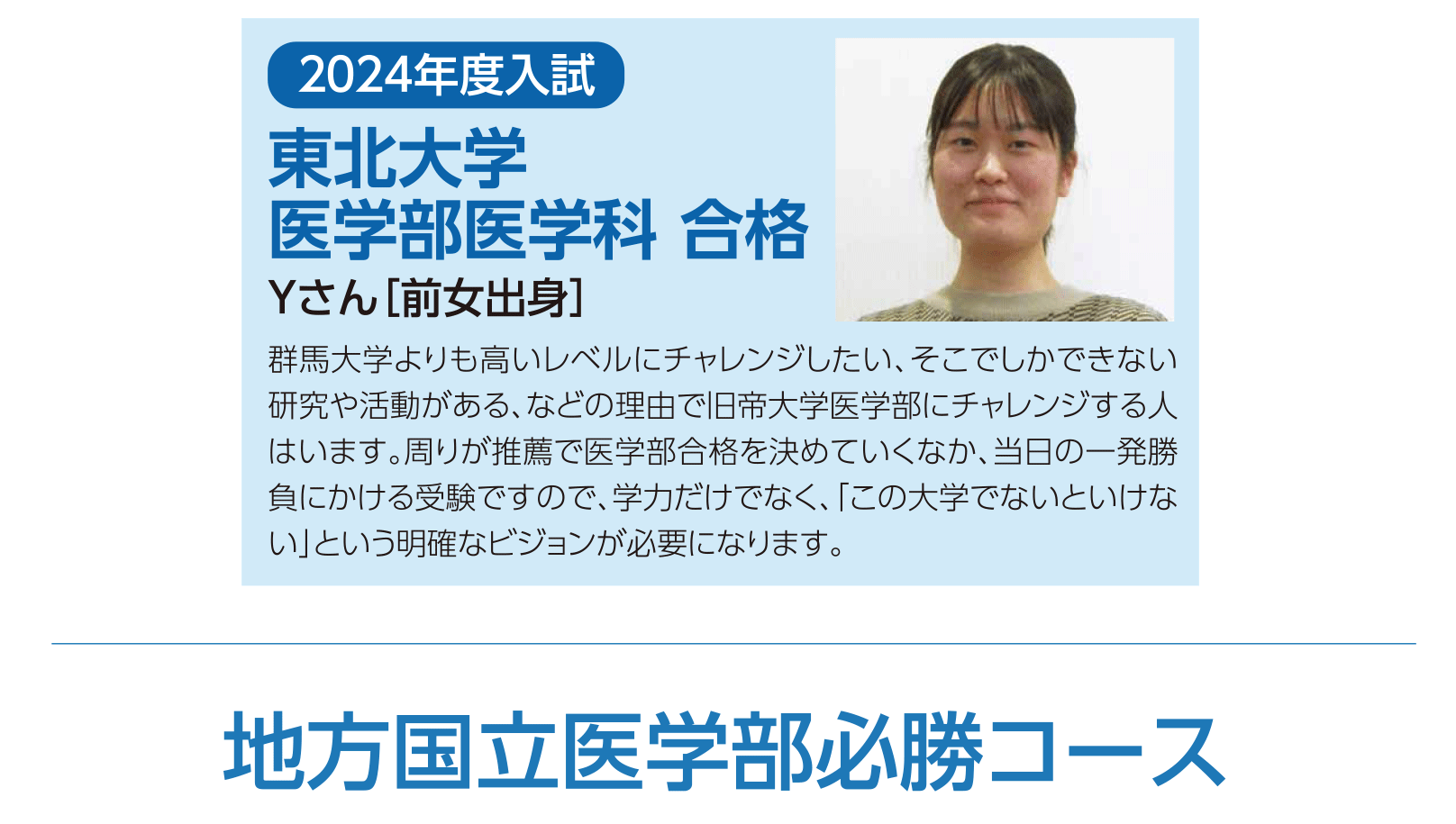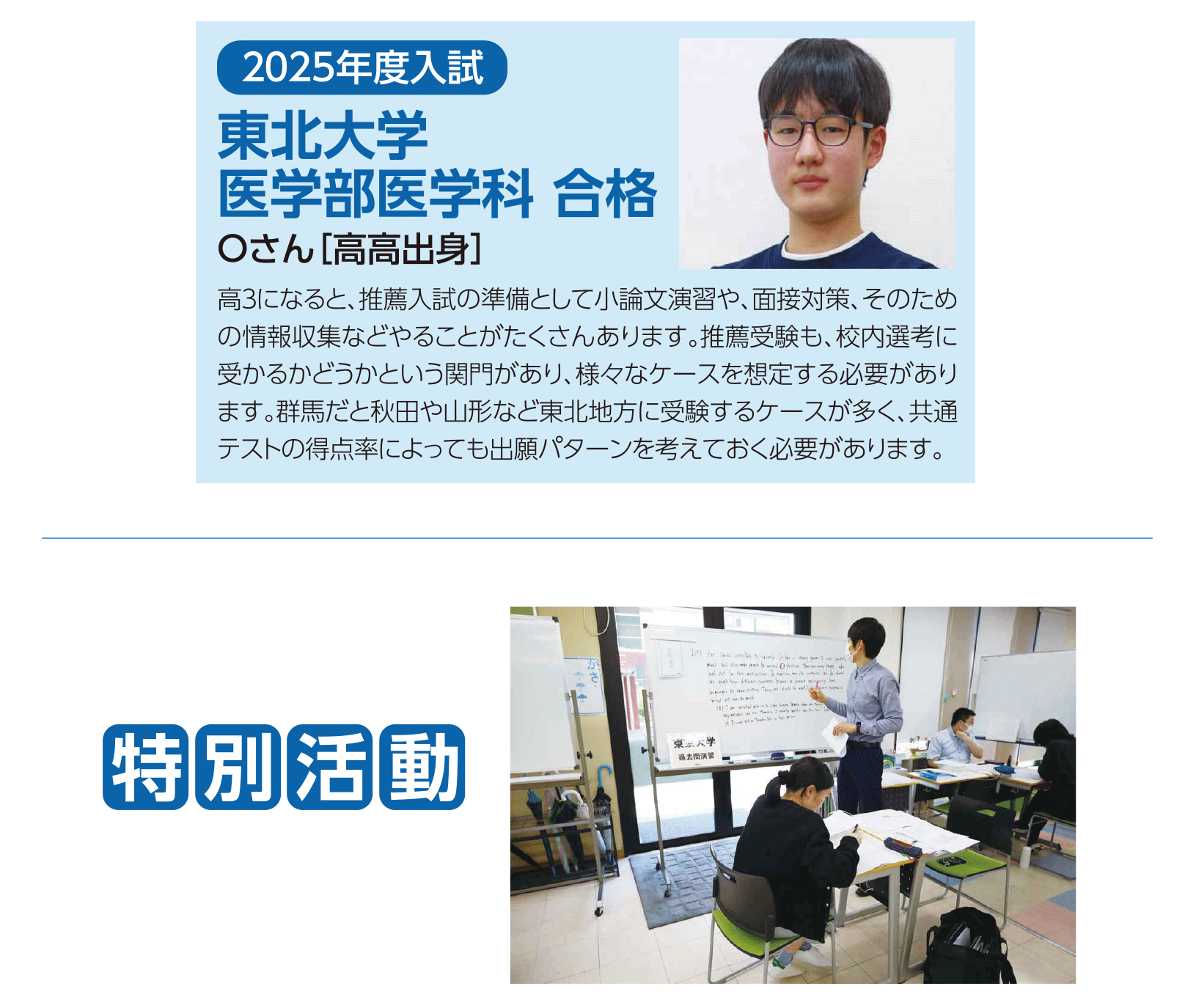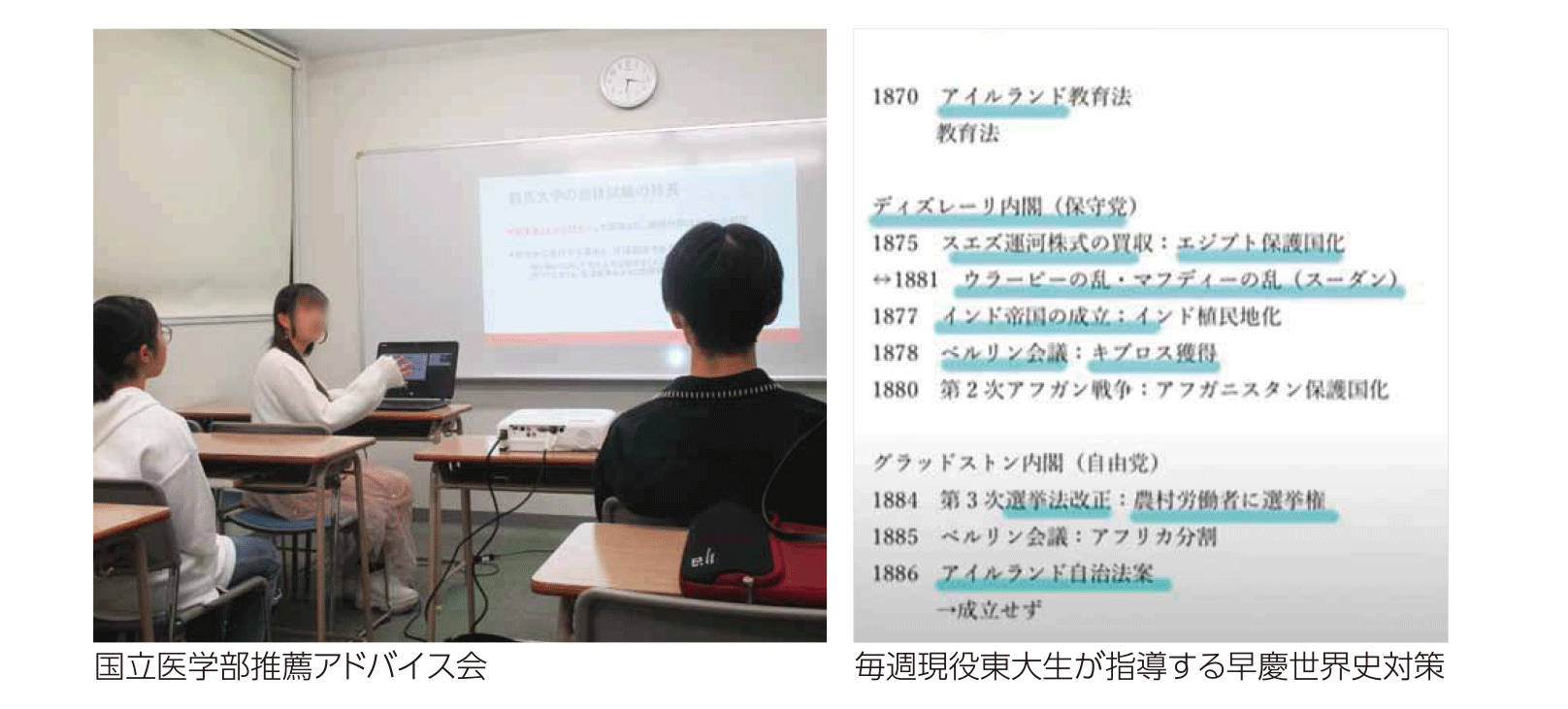夢をゴールにできる塾
うすい学園高等部に通う生徒の中には、小学校や幼児の頃から通い続けてくれる方が多く、3人に1人が東大・京大または国立医学科を目指しています。小学6年生の時点で医師や看護師、研究者を目指している方はおそらく、東大や国立医学科を志望されていることと思います。その時にライバルになるのが、首都圏の中高一貫校生です。首都圏の中高一貫校生は、中3から高3までの4年間で高校範囲を学習します。大学入試までに何度も復習するため、受験対策を有利に進められるという特徴があります。
例えば、わかりやすいのは群馬大学医学部医学科です。群馬大学ホームページの資料によると群馬県出身者は在籍の30%ほどで、大多数が首都圏の出身者になります。
2024年度入試では合格者111名中66名(59.5%)が群馬県外(1都3県)出身者でした。群馬出身者の34名(30.4%)中、ほとんどが推薦入試での合格者で、また浪人生がいることも踏まえると、群馬の現役生は、かなり分が悪いことがわかります。
東京大学も2025年度入試の合格者3014名中、1都3県出身者は1741名で57.8%、群馬出身者は30名で1%でした。小6時に医師や研究者を目指している人が勝負する相手は首都圏の中高一貫校生と言えます。
うすい学園高等部は3カ年計画を完成させて、これをしっかりと実行することで、東大・京大・国立医学部の合格者数は、群馬で随一の実績となりました。それでも、もっと多くの群馬の高校生が、「医学部に行って医師になりたい」「東大でAIを学びたい」と望んでいます。うすい学園グループでは、中学内容を2年間で終わらせ、高校内容を4年間かけて強化すれば、首都圏の中高一貫校に負けずにもっと多くの生徒の夢を叶えられると考え、高等部が行なっていた3ヵ年計画を、6ヵ年計画にブラッシュアップすることにしました。
6年間かけて学力を強化するプログラムと、モチベーションを保ち、将来をしっかりと考える様々なイベントをご用意しています。
1・2年時のカリキュラム
首都圏の中高一貫校と同じペースで数学を履修します。方程式や関数、図形など大学受験数学の土台となる中学範囲を体系的に学びます。中央中等の特進クラスも担当する精鋭講師が学習の取り組み方から指導し、中2時点で群馬県公立高校入試で県内進学校合格レベルの90点を目指します。また月1回ほど高校数学講座という特別クラス※があり、中1から高校数学に触れることができます。将来的にどんな勉強が必要になるのかを感じ取り、成長の指針にしてください。
※高校数学講座は年9回あり、内容は毎回異なります。高崎会場・前橋会場があり、都合に合わせて、会場を変えながら受講いただけます。
高校範囲の英文法を想定し、中1・2時のGAプログラムは「文法重視」で、「超速習」で中学範囲の英文法を履修します。そのなかで長文読解に必要な英文解釈や、大学別二次試験を見据えた英作文を授業に取り入れていきます。併設校舎のウィル個別指導学院でGAプログラムでの学習をフォローをする特別カリキュラムがあるので、中1時点で英語が未経験な方も安心です。
高校数学講座は、中1~中3までの県内の中学生が学校や学年を超えて集まり、高校の定期テストの応用問題として頻出するテーマを約月1回学びます。これから学ぶ高校内容に興味と関心を持つきっかけとなります。東大生や医学部生をはじめ、県内進学校の憧れの先輩が多数駆けつけて、みなさんの学習をサポートしてくれるので、中学範囲の学習に不安がある方も楽しく通えます。
数列は「漸化式」「群数列」など対策すべきテーマが多く、全国の塾の共通テストの対策講座でもなかなか対策に手が届きません。「先取り学習」をして、「難関大学の記述対策」をしている生徒が有利なテストになりました。
対数関数のテキストで掲載した常用対数表が2ページにわたり掲載されました。同じ数学ⅡBCの共通テストで、正規分布表が掲載されるなど、表だけで丸々3ページが使われました。数学を本質的に理解し、問題から誘導や背景などを読み取る力が試されることになりました。
対数関数のテストに掲載した常用対数表が、数学ⅡBCの共通テストで2ページにわたり掲載されました。ほかにも、正規分布表が掲載されるなど、表だけで丸3ページが使われました。数学を本質的に理解し、問題から誘導や背景などを読みとる力が試されることになりました。
少3・4年時のカリキュラム
英語と数学は高校入試レベルを突破し、高校内容に入っている段階です。(高校入試があってもなくても、内容の前提になる)高校内容を塾の先取りだけで身に着けるため、反転授業を導入していきます。生徒は受け身でなく、主体的に学ぶことができ、また塾で習った範囲は自ら問題演習を進められるようにしていきます。内容の前提となる中学範囲の理科・社会は、中3のうちに集中的に演習をして身につけます。
多くの高校が7月から10月にかけて文系・理系の選択、受験に使う理科社会の科目選択があります。将来の指標となる大切な選択になりますので、「社会人の働き方セミナー」や「大学生の大学紹介」なども参考に、自分の興味・関心に従って、「自分がどうなりたいのか」をよく考えて選択します。「この教科が苦手、あるいはやりたくない」という消極的な理由で選ぶことはおすすめしません。
高1からは古典文法という国語教科の授業が始まります。国語は「現代文を強化したい」という声もありますが、いわゆる「時間をかけて積み上げが可能」なのは知識が必要な「古文・漢文」です。学校では「覚えておいて」で終わりがちな古文・漢文の知識を、しっかり身につけていきましょう。また理系は理科基礎範囲、文系は歴史総合範囲の授業も始まります。
文理再編や受験科目の選択が大きな岐路ですので、高等部主催の「社会人の働き方セミナー」で仕事のやりがいや、世の中のリアルを知り、進路選択の糧にしてください。また、高1の夏合宿では共通テスト英数国3教科4科目の過去問5年分を演習します。学力上位の生徒であれば、この時点で80%程度得点できます。最終的な合格ライン(90%)と比較して、現時点での課題を把握したうえで、今後の勉強の指針を決めましょう。
5・6年時のカリキュラム
学校ではほとんど終わっていない歴史の通史を学びながら、論述で書くことを始めていきます(例年、日本史・世界史の教科書が終わるのは高3の10月〜11月で、歴史が最も差がつきやすい科目です。)毎年合格最低点に0.2点や0.7点のプラスで合格する生徒もいて、競走が非常に厳しいことがうかがえます。一方で、うすい学園には僅差でも合格へ導く指導ノウハウがあります。二次数学、入試国語、最難関歴史論述、最難関二次記述英作文など、とにかく「書く」ことを繰り返し、それを専任講師が見ることで高い合格率を実現しています。まずは英語・国語で模試の判定を安定させ、歴史を武器にし、首都圏の中高一貫校生に打ち勝つ力を養いましょう。
歴史と同様に、学校で理科の教科書が終わるのは高3の10月〜11月です。数学は数学Ⅲだけに固執せず、数学ⅠAⅡBCと並行して塾で演習をし、力をつけます。理科は速習コースがあり、高2のうちに物理化学の全範囲を学び終えることで、高3から過去問演習に入ることが可能です。
地方国立大医学部を目指す方は、マーク試験の6教科8科目、筆記試験の英数(必要に応じて、小論文や理科)をバランスよく仕上げる必要があります。高2のうちに共通テストの英数国は得点率80%以上に持って行ければ、高3になって理科・社会の追い込みや推薦対策などに余裕を持って取り組めるでしょう。
高2の4月時点で共通テスト英数国で75%を目指しましょう。夏合宿では東大・京大チャレンジがあり、高3生と一緒に過去問演習をしながら、専任講師による記述添削指導を1対1で受けられます。記述模試を見据えた添削指導と、最終日の面談は成績向上に「確実につながり」ます。高3では、夏合宿で志望校の過去問演習に取り組み、添削指導を通して現在の実力を測り、今後の過去問演習につながる面談指導をおこないます。
精鋭講師陣と東大生・医学生の卒業生で、5教科プラス小論文までトータル指導
うすい学園は、遠方の東大生や医学部生とオンラインで連携し、指導に活用しています。他にも多くの東大生・京大生・一橋生・医学部生が在籍し、毎週指導してくれています。春合宿や夏合宿では、北海道大・名古屋大・筑波大・東北大・金沢大・千葉大など医学部生に限らず、30〜40名の大学生が駆けつけてくれます。「いつでも、どこでも」だけがオンラインの利点ではありません。文系の早慶大対策や、理系の医学部小論文指導など、細かなニーズにも対応し、また群馬の高校の実情を知り尽くした先輩だからこそできるアドバイスがあります。
PAGE TOP