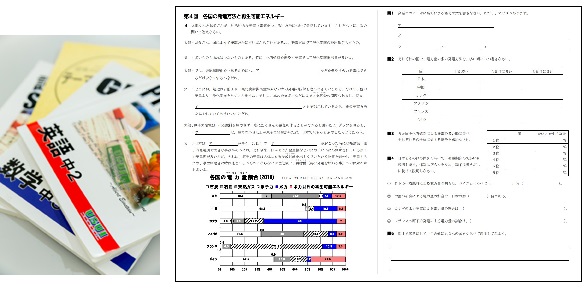「PISA型学力」とは
読解力、思考力、分析力、表現力、コミュニケーション力などを総じて「PISA型学力」といいます。
例えば、資料を見て分析し、結果を他者に伝える/長い文章を読解し、そこから得られたことを自分の言葉で記述する・要約するといった力です。
PISA型学力は、実生活の様々な場面で直面する課題に対して、学校や生活の中で得た知識や経験を活用して自ら積極的に考える力であり、「生きた学力」として注目されています。

うすいの理念は「生徒の可能性を最大限に広げること」。
その理念を実現するため、生徒たちには受験や学校の試験のためだけの学力ではなく、社会に出たときに本当に役立つ力を身につけてほしいと考えています。
その力こそがPISA型の学力であり、PISA型学力を身につける教育は、受験の先の将来を見据えた教育なのです。
うすいでは受験合格をゴールとは捉えていません。
そのため、生徒には志望校だけでなく、その先の将来についても考えてもらう機会も設けています。
※PISA:経済協力開発機構(OECD)が3年おきに実施する、15歳の生徒を対象にした国際的な学習到達度調査。読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について調査する。正式名称は「Programme for International Student Assessment」。
生徒が主役の「考える」を楽しむ授業
PISA型学力を伸ばすためには、生徒が考えることを楽しむ必要があります。
そのため、うすいの授業では解答や解説を講師が一方的に教えることはありません。
まずは生徒たちに自分の頭で考えることを促し、考えたことを隣の生徒と話し合ったり発表してもらうアウトプットの機会を多く設けることでPISA型学力を伸ばす工夫をしています。
講師は、生徒たちが主体的に考え、意見を導き出せるように仕掛けをつくるファシリテーターのような役割を担うのです。
授業を受ける生徒たちからは、
「自分とは違う友達の考えを聞くのが面白い」
「そんな考え方もあるのか!と発見がある」
「うすいの先生は勉強の楽しさを教えてくれる」
という声が寄せられています。
また、文章やデータなどの資料を読み取って考える授業が多いため、使用するテキストの多くを社内で作成しているのもうすいの特徴です。
受動的な勉強ではPISA型学力を伸ばすことはできません。
生徒たちが興味を持ち、楽しんで取り組めるようにテーマ設定や作品選定にも工夫を凝らしています。